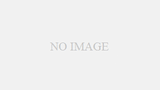日本の株価の月ごとの傾向を12ヶ月分解説します。これらの傾向は一般的なものであり、年によって変動する可能性があるがおおよそこんな感じ。
まとめ
日本の株価は、年間を通じて特徴的な傾向を示します。年初は上昇傾向にありますが、2月と8月は「ニッパチ」と呼ばれる閑散期です。3月と9月は決算期で変動が大きく、4月は新年度の期待感があります。5月は「セルインメイ」で下落しやすく、6月はボーナス効果で高値をつけやすいです。夏は閑散相場ですが、10月から年末にかけては上昇傾向が強まります。ただし、これらの傾向は一般的なものであり、経済状況や世界情勢によって変動する可能性があります。投資判断には総合的な分析が必要です。
1月
年初は上昇傾向にありますが、前年12月の上昇の反動で利益確定の売りも出やすい傾向があります。新年の期待感から買いが入る一方で、年末年始の休暇明けの動きに注意が必要です。海外投資家の日本株への関心が高まる時期でもあり、為替動向にも影響を受けやすくなります。企業の第3四半期決算発表が始まるため、業績への反応も見られます。
2月
「ニッパチ」と呼ばれる閑散月で、相場が比較的静かになります。決算発表が本格化し、業績への反応が見られます。過去にはショックによる急落もあったため、国内外の経済指標や政治情勢に注意が必要です。年度末を控え、機関投資家の動きが鈍くなる傾向がありますが、個別銘柄の動きは活発化することがあります。株主優待権利確定日を迎える銘柄も多く、関連銘柄に注目が集まります。
3月
決算期末で権利取りラッシュとなります。機関投資家の利益確定売りと「ドレッシング買い」が混在し、神経質な展開になりやすいです。年度末を控え、企業の決算対策や機関投資家の運用成績調整の動きが活発化します。配当や株主優待目的の個人投資家の買いも増加します。新年度の経済見通しや政策への期待感から、月末にかけて上昇する傾向も見られます。
4月
新年度の始まりで、新たな投資資金が流入する可能性があります。新入社員の入社や新しい経営計画の発表など、企業の動きに注目が集まります。海外投資家の日本株への関心も高まりやすい時期です。ただし、米国の決算発表シーズンと重なるため、グローバル市場の動向に影響を受けやすくなります。新年度の業績見通しの発表も始まり、個別銘柄の動きが活発化します。
5月
「セルインメイ(5月に売れ)」の格言があり、株価が下落しやすい傾向があります。大型連休明けの利益確定売りや、海外投資家の売り圧力が強まることがあります。ただし、業績好調銘柄には選別的な買いも見られます。株主総会シーズンを控え、企業の株主還元策への期待が高まる時期でもあります。為替市場の動向や、米国の金融政策に関する発言にも注目が集まります。
6月
ボーナス時期で、一年で最も高値をつけやすい月です。配当・株主優待の権利取りや、ETF決算の分配金狙いの買いが入りやすくなります。個人投資家の資金流入が期待できる一方、半期末を控えた調整の動きにも注意が必要です。株主総会が本格化し、企業の経営方針や中長期戦略に注目が集まります。また、日銀の金融政策決定会合の結果にも市場は敏感に反応します。
7月
材料難で小幅な動きになりやすいです。中小型株やテーマ株に資金が向かう傾向があります。夏枯れ相場と呼ばれる閑散期に入りますが、業績発表を受けて個別銘柄の動きが活発化することもあります。海外投資家の動きが鈍くなる一方、個人投資家の存在感が増す時期です。第1四半期決算発表が始まり、業績動向に注目が集まります。また、参議院選挙が行われる年は、政策期待から特定セクターが動くこともあります。
8月
「ニッパチ」の2つ目の月で、閑散相場になりやすいです。お盆休みを挟んで取引量が減少し、株価の変動が小さくなる傾向があります。ただし、海外市場の動向や突発的なニュースに敏感に反応することがあります。第1四半期決算発表のピークを迎え、好業績銘柄への物色が活発化します。月末にかけては、米国ジャクソンホール会議への注目度が高まり、為替市場を通じて日本株にも影響を与えることがあります。
9月
夏枯れ相場から抜け出し、徐々に活況を取り戻す傾向があります。9月決算企業の中間決算発表が始まり、業績への注目度が高まります。秋の株高を期待した買いが入り始める可能性もあります。ただし、米国の9月効果(株価が下落しやすい)の影響を受けることもあるため、海外市場の動向には注意が必要です。為替市場の変動も大きくなりやすく、輸出関連株の動きに影響を与えることがあります。
10月
10月4日の「投資の日」を起点に上昇基調が続くことがあります。大型株を中心に相場環境が好転する傾向があり、年末に向けての期待感から買いが優勢になりやすいです。ただし、海外市場の変動には注意が必要です。第2四半期決算発表が本格化し、業績動向や中間配当の発表に注目が集まります。ハロウィン効果(10月末から翌年5月にかけて株価が上昇しやすい)への期待も高まる時期です。
11月
大型株を中心に相場環境が好転する傾向が強まります。年末に向けての期待感や、海外投資家の買い戻しなどが相場を押し上げる要因となります。ただし、月末にかけては調整の動きも見られることがあります。第2四半期決算発表のピークを迎え、通期業績見通しの上方修正などが相場を後押しします。また、米国の中間選挙が行われる年は、その結果に注目が集まり、日本株にも影響を与えることがあります。
12月
日本の主要大型株は12月に上昇する傾向が強いですが、企業の中間配当金の支払いなどにより、上昇が一服する習性も見られます。年末の「大納会」に向けて、個人投資家の資金流入が期待できる一方で、海外投資家の動向には注意が必要です。年末年始の休暇を控え、徐々に取引量が減少していきますが、年末の日経平均株価の終値は翌年の相場を占う指標として注目されます。